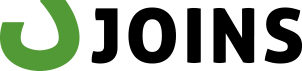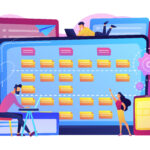副業のリスク、どう回避?山田康成弁護士が解説するセミナーを公開します
企業に雇用される働き方と、副業の働き方にはどんな違いがあって、何に注意する必要があるのでしょうか。JOINSは2月、副業を巡る契約形態やリスク回避について学ぶセミナーを開きました。厚生労働省の「フリーランス・トラブル110番」の事務責任者で、副業に関する法律に詳しい山田康成弁護士(第二東京弁護士会)が、副業をする上で気を付けなければならないポイントを解説しました。副業を始める皆さんに参考にしてもらうために、セミナーの動画を公開します。
今回のセミナーは業務委託契約での個人の働き方に伴う責任とリスクについて説明しました。
セミナー全体をご覧になりたい方は、動画をご覧ください。(約50分ほどあります)
セミナーの内容
- 個人事業主で働く意味とは?
- 報酬の不払い、一方的な契約解消..想定されるトラブル
- 契約書の重要性(委任契約か、請負契約か)
- 副業をする人が加害者になるケースとは?
- 訴訟リスクについて(情報漏洩、著作権侵害など)
- 不正競争防止法の問題
- 相談窓口「フリーランス・トラブル110番」の紹介
具体的に山田弁護士が解説したポイントも紹介します。ざっくりとしたポイントは次の通りです。
- 契約の主体は自分。報酬を得るのも自分、責任・リスクを負うのも自分。
- 業務委託契約(準委任契約)では、プロとしての善良なる管理者として注意義務(善管注意義務)を負う。何の業務で対価を得るか、成果や稼働を認定する基準を明確にすることが大切。
- 受注者が被害者になるケース(発注者からの一方的な契約解消など)もあれば、加害者になるケース(成果物の瑕疵や情報漏洩など)もある。後者では損害賠償請求に発展するケースも。
ポイントをまとめた講演資料はこちらから閲覧できます。
結びに
筆者自身も副業でJOINSで働いています。セミナーに参加した筆者が伝えたいことは、「業務委託契約(準委任契約)」の「委任」という言葉の重みです。副業人材は、高度な専門性とスキルを持って「プロ」として業務を行うことが前提です。働き手(個人事業主)は成果とプロセスに責任を持たなければなりません。
その上で、万が一の時のことを考えて備えをしておくことも、副業人材と企業側が安心して気持ちよく良い仕事をしていくために大切なことだと感じました。セミナーの後半では、備えの一つとしてフリーランス特有のリスクを補償する賠償責任保険も紹介されました。
厚生労働省は3月26日、フリーランスの指針「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」を公表しました。フリーランスを自営業者とみなし、独占禁止法などで保護する内容で、不平等な取引条件の抑止力になると期待されています。
JOINSは、副業・兼業という働き方に一歩踏み出す皆さんの役に立つ情報を、今後も発信していきます。
投稿者プロフィール