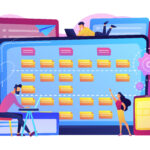シューカツと何が違う?副業先との「面談」で意識したい3つのポイント

JOINSは、地域企業と副業人材のマッチング支援を通して、両者の間に「長く、お互いに応えあう関係」が生まれていくことを目指しています。
副業人材が「長く頼りになる存在」になるためには、はじめのステップとして、まず地域企業から示された課題に真摯に取り組み、小さくても具体的な成果(スモールウィン)を実現することが重要です。その経験がお互いの信頼のベースを築き、「次の仕事」が生まれ、中長期的な関係につながっていきます。
企業にとってスモールウィンをイメージしてもらえる人材の特徴とは――。前回(応募編)に続き、今回はマッチングプロセスの「面談」に着目。副業人材に対して、「この人となら一緒に良い仕事ができそうだ」と地域企業が感じるポイントについて考えてみます。
目次
「面談」の目的は、期待(予感)の確度を上げること

面談(特に一次面談)は、企業と人材が募集・応募の段階で伝えきれなかった情報をお互いに交換して、「どのような課題解決が期待されているか」の認識をすりあわせる場です。とりわけ企業にとっては、応募内容から読み取った「この人とだったら良い仕事ができるかもしれない」という期待(予感)の確度を上げるための場とも言えます。
前回の記事で、面談に進む「応募」内容の共通点として次の3つを紹介しました。(詳しくはこちら)
- a. ○○の経験がある(CAN)+自分がやりたい(WILL)がある
- b. 自分の中の「正解」だけでなく、相手との「納得解」を探る構えがある
- c. 相手が見ている「風景」を想像して書いている
企業側の経営者や採用担当者は、例えば上の3つのようなポジティブな印象(一度会って話を聞いてみたいと感じた期待・予感)が正しかったのか?を、人材との会話を通して(面談の場で)確かめたいと思っています。
「この人と仕事がしたい」と企業が思う瞬間とは

地域企業が「この人に決めた」理由(JOINSの例)
JOINSを通じて副業人材との契約が成立した地域企業に、「なぜその人と一緒に仕事をしたいと思ったのか」を尋ねると、次のような答えがよく返ってきます。
- 経歴が立派な方からたくさん応募があったが、最後は人柄で決めた。(当社の社員と馴染めそうだと感じた)
- 無理のないところから変えてくれそう。いいところは残しつつ、知識やスキルの足りない当社に寄り添って進めてくれそう。
- 当社のことをよく理解していて、話が早かった。また、話しているうちに漠然としていたことが整理できた。
企業が確かめたいことは、「応募」も「面談」も変わらない
これらを見ると、先に挙げた良い「応募」の特徴とも重なる部分が多いことがわかります。本質的なこと(企業が確かめようとしていること)は、応募でも面談でも大きく変わらないのかもしれません。企業は、応募を受け取った時点での限られた情報(文字のみ)を、面談の場で得られる追加の情報(言葉や表情、雰囲気、会話の「間」など)で補いながら、その人材に対して抱いている期待感が妥当なものであるかを確かめていると言えそうです。
(参考)企業がどんな人と一緒に仕事をしたいと考えているのか?については、JOINS代表・猪尾が寄稿したこちらの記事もぜひご覧ください。
副業の採用面談を受けるまでに考えたい、現実的な「3つのポイント」(ダイヤモンド・オンライン|2021.3.2)
就職や転職の「面接」との違いは?
この記事を読んでいる皆さんの中には、特定の企業に社員として雇用されながら副業をしている(または始めようとしている)方もいるかもしれません。筆者もその一人です。そんな皆さんが一度は経験された?であろう就職「面接」と、副業先候補との「面談」では、どのような違いがあるでしょうか。その違いを知ったうえで、どのような心構えで面談に臨めばよいのでしょうか。
就職「面接」も副業「面談」も、「再現性」を推し量る場
一般的な就職支援セミナー等でよく言われるのは、企業にとって「面接」は、目の前にいる人材の語る経験や実績が、やや条件の異なる仕事や環境においても応用できそうなものか(再現性)を推し量る場であるということ。
再現性があることを企業に感じ取ってもらうために、過去の事実(どのような状況で、どのような役割を担い、何を実行し、どのような結果を得たか)と、経験(その事実から何を学び、何を感じ、どんな自分になったのか)を説明します。
また、語られる内容そのものだけでなく、その時の表情や口調、語彙、質問に対する返答の簡潔さや明瞭さ(会話が噛み合っているか)なども、仕事の場面で発揮される思考力やコミュニケーション力を想像するための材料になります。
副業「面談」の特徴は、前提とする時間軸が短いこと
副業でも「再現性」は求められますが、前提とされている時間軸(活躍するまで待てる時間の長さ)が短いため、将来どのような存在になっていくかよりも、小さくても具体的な成果(スモールウィン)と、そのための実行力が期待されます。
また副業人材の場合は、(無期雇用の新入社員と違って)職場メンバーとの関係構築に十分な時間と手間をかけられません。そのため、特に現在はリモートワーク中心で接点が限られることも相まって、業務がスタートする段階からある程度「安心して任せられそう(前に進めそう)」と予感してもらえるかが肝になります。
地域の伝統や暮らしを大切にしながらビジネスを営んでいるJOINSのパートナー企業からは「同じ思いで仕事をしてくれる人を待っています」という声がよく聞かれ、副業≒仕事上のドライな関係と割り切らず、人材との信頼関係を重視している姿勢が伺えます。

企業側が副業人材の採用に慣れていない場合も
1つ注意する必要があるのは、副業人材を求めている企業であっても、これまで上表の左側のような人材採用(無期雇用)の経験しかない場合がある点です。
短期間でスモールウィンを実現するためには、「具体的に実現したい状態は?」「そのために企業がサポートできること・できないことは?」「進捗連絡の方法や頻度のルールは?」などについて企業と人材がお互いの認識を揃えることが大切です。
しかし副業人材の活用に慣れていない企業の場合、具体的な期待や要望を言葉にする(仕様を決める)のが得意でないケースも珍しくありません。どのように仕事を切り出したらよいか。自社メンバーをリードしてもらえるのか。ふつうはどれくらいで効果が出るものなのか。そのあたりを言語化していくところから手伝う必要があるかもしれません。そんな可能性も念頭に置いて「面談」でのコミュニケーションを重ねていけるとよいでしょう。
面談はお互いの期待感をすりあわせる場
今回は、マッチングにおける「面談」に着目し、「応募」との関係も踏まえながら、地域企業が副業人材を選ぶ際のポイントについて紹介しました。また副業人材として、スモールウィンのイメージを企業と共有するにはどのようなスタンスで面談に臨むと良さそうか、一般的な就職面接との比較も交えながら考えてみました。
地域企業にとっても、そこで副業を始めようとする皆さんにとっても、「面談」という場が、共に良い仕事をするパートナーとしての期待感を率直に確認しあえる場になるように、JOINSも引き続きサポートしていきます。
(イラスト|freepik.com)
シリーズ スモールウィンにつながる副業人材の特徴
【スモールウィン】地域企業が抱える課題に副業人材が向き合い、「小さくても具体的な成果」を出すこと。それがお互いの信頼のベースをつくり、「次の仕事」が生まれ、持続的な関係につながっていくとJOINSは考えています。
投稿者プロフィール

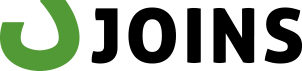
の面談の違いは_2-1024x588.png)